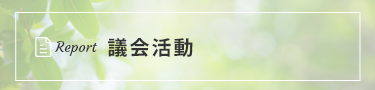2025年10月23日
安藤たい作区議が「小山三丁目第一地区本組合設立申請取り下げ、『直近総事業費』・『資金計画』・『工期計画』・『時価補償費』等の確認と公表を求める陳情」への賛成討論を行いました。
2025.10.23 安藤たい作区議
日本共産党品川区議団を代表して、令和7年陳情第41号「小山三丁目第一地区本組合設立申請取り下げ、『直近総事業費』・『資金計画』・『工期計画』・『時価補償費』等の確認と公表を求める陳情」への賛成討論を行います。
小山三丁目第一地区は、武蔵小山駅前に現在建っている2棟のタワーマンションに加え、アーケードをまたいだ敷地に更に40階建てタワマンを建てる計画。今年5月に再開発本組合設立申請書が出され、8月に住民から意見陳述が行われました。このまま申請が認められ再開発組合が立ち上がり権利変換等の手続きが終わると、地区内の資産は組合の所有になり、強制執行など法的権限も組合に与えられることになる重大局面です。
陳情41号は、組合設立申請の取り下げを求めつつ、以下4項目を求めるものです。第1に、開発における意思決定権があまりに小さい分譲マンション区分所有者が多数いる当該地区で再開発を計画したことが妥当なのかを問い、第2に、都市計画決定の判断を行った都市計画審議会の抜本改革を求め、第3に、都市計画決定後に建設費高騰など再開発を巡る情勢が激変する中、現時点での総事業費や資金計画等の公表を求め、第4に、国会決議に基づき、区に再開発準備組合理事長との会談を実現させるよう求めるものです。
当該地区での権利者の同意は84%にとどまり、実人数で35名が不同意、反対運動も続く中、莫大な税金を投じ既存の商店街を大きく損ない、インフラパンクやCO₂排出などの環境にも大きな影響を与える開発計画の認可申請は取り下げられるべきです。その立場から以下、陳情への賛成理由を述べます。
1点目は、上位計画を錦の御旗にし再開発を進めるやり方は止めるべきという問題です。
区は、当該地区が、まちづくりマスタープランで地区活性化拠点に位置づけられ、にぎわいと活力ある市街地を形成すると書いてあると説明します。しかし、5棟の分譲マンションが含まれ148人もの区分所有者が住んでいるこの地区で再開発を行うこと自体、無理があります。法律上ではマンション1棟が1人と数えられるため、148人はわずか5人ということにしかなりません。区は、「マンションの区分所有者も平均して84%の同意を取っている」とも説明しますが、計画を策定してきた再開発準備組合の理事会にはマンションからの参加はわずか1名ずつでした。しかもその理事にも、「理事会での内容はマンション住民には知らせないように」と箝口令がしかれていた、と聞いています。これが84%同意に至る過程の内実なのです。
委員会審査で区は「区民の意見を聞き、議会からの同意も得て策定したマスタープランに従ってまちづくりを進めることが今現在必要なまちづくりの方向性」と述べましたが、順番があべこべです。「まちづくりとは、住民自らがまちのあるべき姿について話し合いを重ねながら形作っていくプロセス」、「まちづくりの主体はそこに住む地域住民」との区長答弁とも矛盾します。上位計画を振りかざし、弱小地権者の権利を軽視するようなやり方に目をつむり、超高層開発計画を進めることは止めるべきです。
2点目は、都市計画審議会のあり方を抜本的にただす必要がある点です。
陳情者は都市計画決定の判断を下した都市計画審議会を傍聴し、区長選任学識経験者・有識者の発言は一言もなく短時間で閉会、税金を229億8千万円を投入して1,500名の地権者・住民を追い出す開発が決定された、と厳しく告発しています。現在、都計審の会長は、区の元都市整備部長が務めていますが、開発推進の高橋区政の下でまちづくりの責任者を務めてきた方を任命するのは、「再開発を推進するための配置」とのそしりは免れません。また、会長職務代理者も、渋谷区の元まちづくり部長となっており、再開発を推進する布陣は盤石なものとされています。
都計審で意見が出ないのは、判断に必要な材料が提供されず、意見の出しようがないからです。私は「現地視察の実施や、都市計画案の住民説明会への参加を案内するなど、改善を」と質問しましたが、区は「審議会の中で提案されれば区として抗うことはしない」旨、答弁。また、審議会の体制についても最終的には、「指摘を受け止めて、今後考えていきたい」などとも述べました。それぞれ改善を強く求めます。
3点目は、超高層再開発に対する、膨れ上がる税金の大盤振る舞いの問題です。
陳情者は、投機マネーの横行、建設費の急騰や国の補助金削減の方針など、再開発を巡る情勢の激変の下、見通しがない再開発に突っ込むのではないかと不安と疑念を抱いています。中野サンプラザ跡地の再開発では、都市計画決定後、工事費が当初の想定を900億円以上も上回る見込みとなり、野村不動産が事業認可申請を取り下げました。解体工事がほぼ完了していた新宿駅の西南口地区でも、建設費の高騰で施工会社が決まらず工期完了時期が未定となりました。
小山三丁目の事業費は、事業認可申請によれば963億1000万円、補助金額は229億8000万円との答弁でした。しかしこれは工事着手までにどこまで高騰するかは未知数です。現に、区内で工事中の東五反田二丁目第三地区再開発は、都市計画審議会時には税金投入見込み額が91億円と答弁されていました。ところが、先日の決算総括質疑ではいつの間にか220億円、2.4倍になっていると判明。この間、国の新たな資材高騰分を補助する制度が創設されたことを差し引いても、異常な高騰です。高騰分の129億円だけでも、毎年20億円捻出しているウエルビーイング予算の6年分にあたります。私は「事業認可後に大幅に事業費・補助金額が上がったとしても、その認可は有効と言えるのか」と問いましたが、区は、認可を変更するわけでも取り下げるものでもないと述べました。大企業を潤す超高層開発には認可後に補助金がいくら膨れ上がっても問題とせず、湯水のように税金が注がれ続ける。こんな税金の使い方は止めるべきです。
4点目は、理事長と心配する住民との懇談です。
昭和44年衆議院建設委員会における「都市再開発法案に対する国会決議」には、「市街地再開発組合の設立にあたつては、事業内容等を周知徹底し、同意を得られない者の立場も十分に考慮して、極力円満に設立手続を進めるよう指導すること」とあります。この立場や、区長答弁に照らせば、区は開発に同意できない住民が望んでいる再開発準備組合理事長との会談について、最大限の努力を払い実現させる責任があります。この点、決算総括質疑で区は、双方の主張の隔たりに関しても「会談の実現に向け、準備組合ともあらためて調整を進めており、現在、一部の地権者以外の方も出席や発言できるよう鋭意調整を行っている」と述べました。万が一にも、会談が実現しないうちに東京都が事業認可を行うことなどあってはなりません。あらためて責任を果たすよう、強く求めます。
以上、賛成理由を述べてまいりました。陳情を採択し、住民本位のまちづくりへ転換させるよう、議場の皆様へ呼びかけまして、私の賛成討論を終わります。